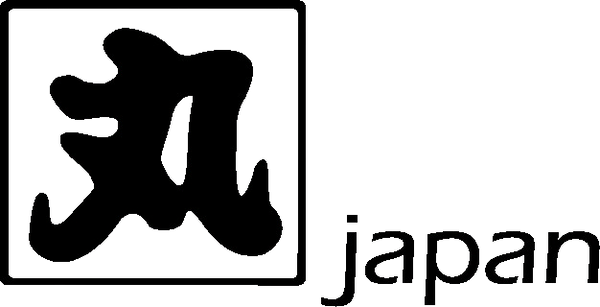木曽漆器と中山道
歴史が息づく街道で、旅の思い出と美を巡る
江戸時代の風情を色濃く残す中山道。その中でも、豊かな自然と歴史が織りなす木曽谷は、古くから多くの旅人を魅了してきました。ここには、日本の伝統工芸である木曽漆器が育まれ、街道の賑わいとともに発展した物語が秘められています。
単なる宿場町としてだけでなく、英雄たちの足跡、詩歌に詠まれた絶景、そして職人の技が息づくこの地で、あなたも歴史と美を巡る旅に出かけませんか?
中山道と木曽漆器:旅が育んだ工芸の華
かつて江戸と京を結ぶ五街道の一つとして栄えた中山道。特に木曽路は、その険しい山々と清らかな流れが織りなす情景が、多くの文人墨客を魅了し、詩歌や浮世絵の題材となりました。
歌川広重の描いた「木曽街道六十九次」のように、その趣深い風景が世に知られるにつれて、街道や宿場は旅人で一層賑わいを見せるようになります。
そんな旅人たちが求めるのは、道中の疲れを癒す宿だけでなく、旅の思い出となる品々でした。木曽谷の豊かな木材資源と、古くから伝わる漆の技術が結びつき、木曽漆器は宿場町の活気とともに発展を遂げました。
旅籠に宿泊する人々は、木曽の美しい自然が育んだ漆器を求め、生産・販売・流通の拠点として、この地は一層の繁栄を極めていったのです。
木曽義仲と巴御前:英雄たちの足跡が刻まれた地
木曽谷は、単に美しい景観と工芸品だけの地ではありません。平安時代末期には、**木曽義仲(源義仲)**がこの地で挙兵し、平家を打ち破って京へと駆け上った歴史が刻まれています。
彼の勇猛果敢な戦いは、巴御前という女武将の存在とともに語り継がれ、この地の歴史に一層の深みを与えています。木曽の山々を駆け巡った彼らの息吹を感じながら、街道を歩けば、その物語がより鮮やかに蘇るかもしれません。
木曽の絶景と信仰の山:詩情豊かな情景
木曽谷の魅力は、その雄大な自然にもあります。空高くそびえる御嶽山は、古くから信仰の対象として人々に崇められてきました。また、日本百名山の一つである木曽駒ヶ岳は、四季折々の美しい姿で訪れる人々を魅了します。
これら山々の麓に広がる渓谷や森林は、まさに**「木曽八景」**と謳われるにふさわしい、詩情豊かな情景を織りなしています。漆器の深みのある色合いは、もしかしたらこの地の自然の色、光沢を映し出しているのかもしれませんね。
奈良井宿と木曽平沢:漆の里を巡る小径
木曽路の中でも特に栄えたのが、「奈良井千軒」と謳われた奈良井宿です。中山道三十四番目の宿場町として、その規模と賑わいは木曽街道随一を誇りました。国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されており、江戸時代の面影を色濃く残す町並みは、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わわせてくれます。
そして、奈良井宿と並んで木曽漆器の生産地として発展してきたのが、漆工町・木曽平沢です。こちらも国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、漆器店や工房が軒を連ねる町並みは、漆の香りと職人の息遣いが感じられる独特の雰囲気を醸し出しています。
中山道三十三番目の宿場であり、木曽十一宿の北端にあたる贄川宿(旧楢川村)から、漆器の伝統が息づく木曽平沢、そして「奈良井千軒」の賑わいを今に伝える奈良井宿へと続く道は、木曽漆器の歴史と文化を肌で感じられる最高の散策路となるでしょう。
中山道の宿場と木曽漆器の物語は、ただ古い歴史を語るだけではありません。そこには、人々の暮らし、地域の特色、そして美しいものづくりへの情熱が息づいています。ぜひ一度、この歴史ある街道を訪れ、木曽漆器が紡いできた物語に触れてみてください。
奈良井宿は、「奈良井千件とうたわれ」、木曽街道随一の宿場として栄え、漆工町木曽平沢とともに木工品や漆工品の名産地として発展してきました。
旧楢川村である、中山道33番の宿、関所贄川宿(木曽11宿の北端)から漆工町木曽平沢(国・重要伝統的建造物群保存地区)を経て、中山道34番の宿、奈良井宿(国・重要伝統的建造物群保存地区)までの道中を歩くのも良いでしょう。

是より木曽路の碑・木曽路最北端(贄川宿)