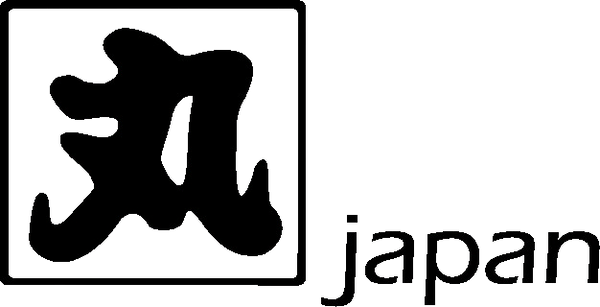問屋の蔵で気づいた、木曽漆器の『時間』
職人でない者が、漆器を語ってもいいのか
私は職人ではない。漆を塗ったことも、木地を削ったこともほとんどない。木曽の漆器問屋で、蔵の中の「時を経た器たち」と向き合う日々を送っている。
蔵に眠っているのは、中古品ではない。かつて作られ、何らかの理由で残った器たちだ。プラスチック製のものもある。派手な柄のものもある。正直に言えば、いわゆる「伝統工芸の逸品」ばかりではない。
最初は、それが少し気になっていた。でも今は、それでいいと思っている。
問屋というのは、職人と消費者の間に立つ存在だ。職人の理想だけでも、消費者の都合だけでもなく、その時代時代の「必要」に応えて様々なものを扱ってきた。蔵の中の多様さは、ある意味でその歴史の証なのかもしれない。
ある日、ふと気づいたことがある。
蔵の中で何年も、ときには何十年も眠っていた漆器を手に取ったとき、新品とは明らかに違う質感があった。漆は、ゆっくりと硬化を続けて艶を変えている。均一な美しさでは表現しきれない、漆器本来の奥行きと趣。木と漆は「熟成」するのだ。
これが「塗趣(としゅ)」なのだと、この仕事を通じて少しずつ理解してきた。
職人の世界は素晴らしい。でも、時間を重ねた器を扱う問屋にも、独自の役割があるんじゃないだろうか。それは、「時間」という名の職人を、もう一人加えることなのかもしれない。
蔵から出した器を手に取ると、時々考える。この木は、いつ伐られたのだろう。樹齢は。どんな森で育ったのだろう。どんな職人の手を経て、ここに辿り着いたのだろう、と。
私は職人ではないから、技術的なことを語る資格はない。ただ問屋として、この器たち(潤い)を次の誰かに手渡す役割がある。完璧な工芸品としてではなく、時間を重ねた個性あるものとして。
「塗趣(としゅ)」という言葉を、当店では大切にしている。
それは新品の完璧さではなく、不均一な表情、時が加えた味わいを愛でる心だ。職人が作り、時間が育て、問屋が見守り、そしてあなたが使う。その連なりの中に、木曽漆器の本当の豊かさがあるんじゃないかと信じている。
私は職人でも工芸家でもない。ただの問屋だ。でも、だからこそ見えるものもあるような気がする。
蔵の中の器たちを見るたび、思う。これらはただ「出番を待っていた」のだと。
店主