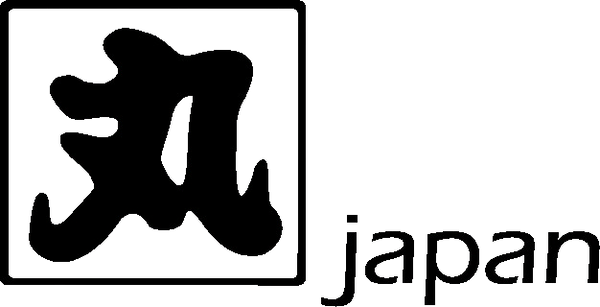【蔵出殿】かく丸漆器問屋


カシュー塗:カシューナッツ
カシュー塗の特徴 カシュー塗料の成分は、ウルシ科カシューナットノキから抽出される天然成分を主成分として含みます。主な成分はカシューナッツシェルオイルであり、これが塗料の特性を決定します。
カシュー塗:カシューナッツ
カシュー塗の特徴 カシュー塗料の成分は、ウルシ科カシューナットノキから抽出される天然成分を主成分として含みます。主な成分はカシューナッツシェルオイルであり、これが塗料の特性を決定します。